ストーンの重み 時の重み
切符は、1枚。
その切符を手にするためのたたかいの舞台は、
北見市・常呂の
アドヴィックス常呂カーリングホール。
4年前の2013年11月にオープンした、
「カーリングの街」北見市常呂のシンボル的存在だ。


女子カーリング平昌五輪代表決定戦の取材で
5年ぶりに、この地を訪れた。
前回、特番の制作のために訪れたとき、
このホールの姿はまだなく、
その隣に今も姿を残す、日本初のカーリング専用施設、
旧・常呂カーリングホール(奥の建物)が取材の場所だった。

訪れたのは、シーズンを通して行われる、地域リーグ戦の開幕の日。
この日を待ちわびたように
老いも若きも関係なく、続々とホールにカーラーたちがやってきて、
試合を楽しんでいた。
いや、正確に言えば、試合だけでなく、
試合後に咲かせる「カーリング談義」を含め、
「暮らしの中のカーリング」を満喫していた。
常呂とカーリングのつながりは
紙の上では知ってはいたが、
現場で目の当たりにするその風景は、
いい意味で衝撃だった。
カーリングという一つのスポーツで
これほどに街の人たちが自然につながり合っている。
「誰かの」スポーツではなく、
「私たちの」スポーツと何のためらいもなく言える風景は
そうした求心的なものを持たない街で育った
(という意識を持っている)人間には、
羨望に値するものだった。
あれから5年。
初めて入った、新しいカーリングホールには、
五輪をかけた、たたかいの緊張感と、
日本最高峰のカーリングの試合を観戦できる喜びが入り混じった
自然で、心地よい空気があふれていた。
ちょっとの時間では、この空気は作れない、と思った。


オレンジを基調とした中部電力の応援も温かく、心地よいものだった。
長野のカーリングを取り巻く空気が伝わってきた
カーリングを観て、プレーして、語らって、という時間を
それぞれの人生を歩んでいく中で重ねた人たちが
一つの場所に集うことで醸し出される、そんな空気。
語弊を恐れず言えば、
「にわか仕込みではない、懐の深い緊張感」といったところか。
そしてそれは、足を踏み入れる前に、
そうあって欲しいと思っていたものと同じだった。
2階にある交流サロンには、
常呂のカーリングの歴史を紹介するコーナーがある。
(旧ホールにもあった)


このブログで以前紹介させてもらった、
日本のカーリング黎明期に
指導者の育成に尽力した
「日本カーリングの父」と呼ばれる元世界王者、
ウォーリー・ウルスリアックさんの
若かりし頃の姿や、
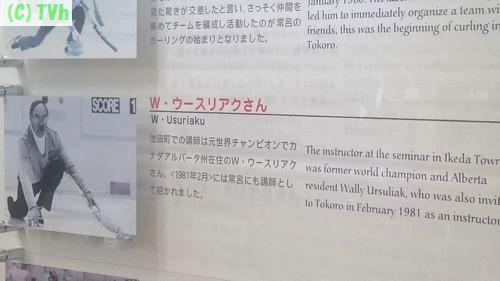
こちらでは「ウースリアク」さんと紹介されていた
そのウルスリアックさんの指導を受け、
常呂にカーリングを根付かせた
常呂カーリング協会初代会長・故小栗祐治さんの雄姿があった。
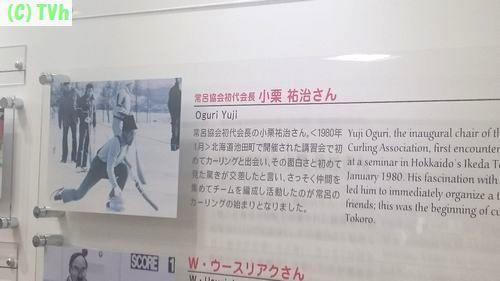
こうした方々が蒔いた種が、
芽を出し、葉を広げ、花開いたのが
件の、ホール内に広がった空気なのだ。
常呂の多くのカーラーたちがそうだったように、
今回五輪代表を手にしたLS北見を、
7年前、ゼロから立ち上げた本橋麻里選手も、
幼き頃、小栗さんにその才能を見出された選手の一人。

「カーリングのために人生があるのではなく
人生の中にカーリングがある」ことを求めて、
故郷に戻り、仲間を集い、
スポンサーを見つけ、地域とつながって、
そして、勝つ。
彼女は今回の五輪出場を
「第一目標はクリアした」と表現したが、
その向こうの、第二、第三の目標の更に先には
彼女のこの言葉を、より広く、より深く実現していくことがある。


その発想を育んだのは
まぎれもなく、この地で流れた時間である。
選手たちが投じるストーンは
スコットランドのアルサクレッグ島で産出した
およそ20㎏の花崗岩。
以前、抱えさせてもらったことがあるが、
しっかり踏んばらないと、腰砕けになるレベルのものだ。
そんな重さのストーンを、
1センチ、あるいはそれ以下のレベルで
氷上を滑らせていくたたかいを経て、
LS北見は、五輪の切符をつかんだ。
ときに、意思を持った生き物のように
繊細に氷上を動いたそのストーンには
この地で、カーリングに携わった人たちが紡いだ
時間の重みも、加わっていたのかも知れないと思った。










